ホーム > 市政情報 > 政策・企画・行政運営 > ユニバーサル(共生)の推進 > 札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例 > オープンハウス(パネル展)による意見募集
ここから本文です。
オープンハウス(パネル展)による意見募集
「(仮称)札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例」の検討に当たっては、条例素案の内容などを分かりやすく紹介するパネルの展示と併せて、市民の皆様からご意見をいただくオープンハウス形式での意見募集を行いました。
(令和6年(2024年)11月実施)開催結果
「(仮称)札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例」の素案などをパネルでご紹介するパネル展(オープンハウス)を下記のとおり市内2会場で開催いたしました。
1.開催概要
タイトル
共生社会の実現に向けたオープンハウス
日時及び場所
| 日時 | 場所 | ||
| 1 |
令和6年(2024年)11月22日(金曜日) 9時30分から17時00分まで |
アクセスサッポロ (札幌市白石区流通センター4丁目3番55号) ※にぎわい市場さっぽろ2024内 |
|
| 2 |
令和6年(2024年)11月23日(土曜日) 9時30分から17時00分まで |
||
| 3 |
令和6年(2024年)11月24日(日曜日) 9時30分から16時30分まで |
||
| 4 |
令和6年(2024年)11月26日(火曜日) 10時00分から17時00分まで |
札幌駅前地下歩行空間(チ・カ・ホ) 憩いの空間北1条東 |
|
参加人数(意見シート等の枚数)
596人(内訳 1:113人、2:170人、3:156人、4:157人)
2.主な意見(抜粋・要約)
|
1.条例素案全般に関する意見 |
|
|
2.多様性を尊重したまちづくりに関する意見 |
|
| 3.包摂的なまちづくりに関する意見 |
|
| 4.市(行政)・市民・事業者との協働に関する意見 |
|
| 5.市の役割や基本的施策に関する意見 |
|
| 6.市の役割や基本的施策に関する意見 |
|
3.展示パネルの内容
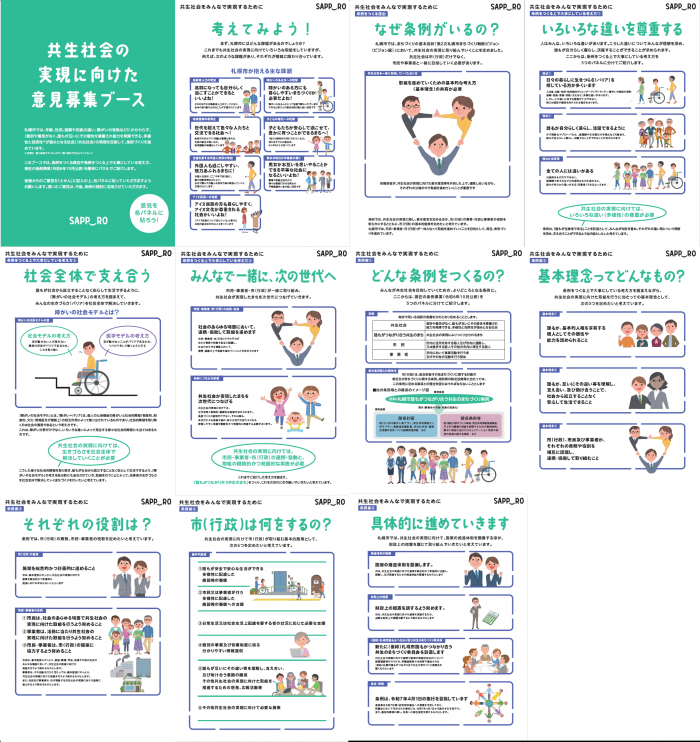
4.開催案内チラシ
共生社会の実現に向けたオープンハウス開催案内チラシ(PDF:1,126KB)

(令和6年(2024年)8月実施)開催結果
「共生社会バリアフリーシンポジウムin札幌」の同時開催イベントの一環として、「共生社会の実現に向けた意見募集ブース」を設置しました。
当該ブースでは、条例の骨子案を紹介するパネルを展示の上、付箋や意見シートで自由に意見を書き込めるようにし、イベント参加者を始め多くの方からご意見をいただきました。
1.開催概要
- タイトル
共生社会の実現に向けた意見募集ブース - 日時及び場所
日時:令和6年(2024年)8月4日(日曜日)10時00分から18時00分まで
場所:D-LIFEPARK(札幌市中央区北3条西4丁目 D-LIFEPLACE札幌地下1階) - 参加者及び参加人数
参加者:イベント参加者を含む市民等
参加人数(付箋等の数):172
2.主な意見(抜粋・要約)
|
(1) (仮称)共生社会推進条例の全般に関する意見 |
|
|
(2) 多様性の尊重に関する意見 |
|
| (3) 包摂的なまちづくりに関する意見 |
|
| (4) 市(行政)・市民・事業者との協働に関する意見 |
|
| (5) 市の役割や基本的施策に関する意見 |
|
3.展示パネルの内容
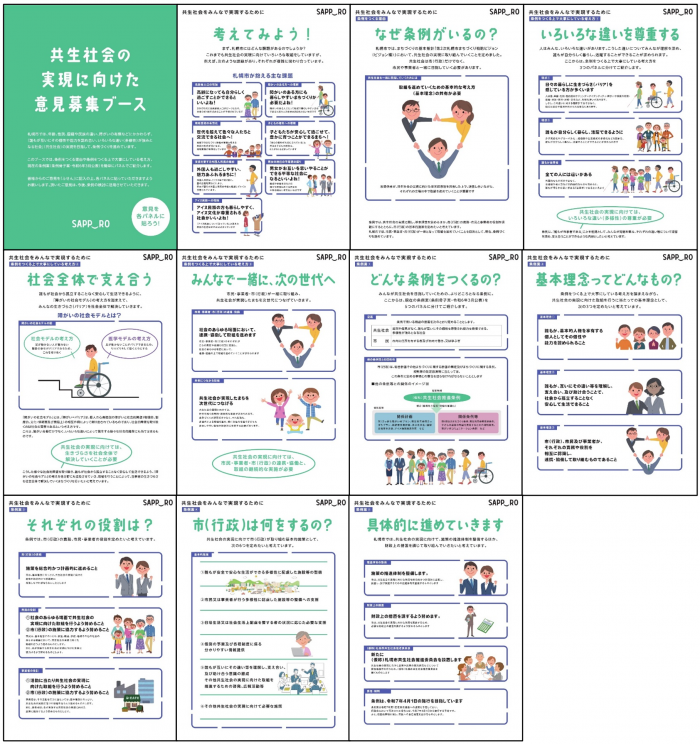
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.